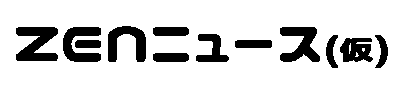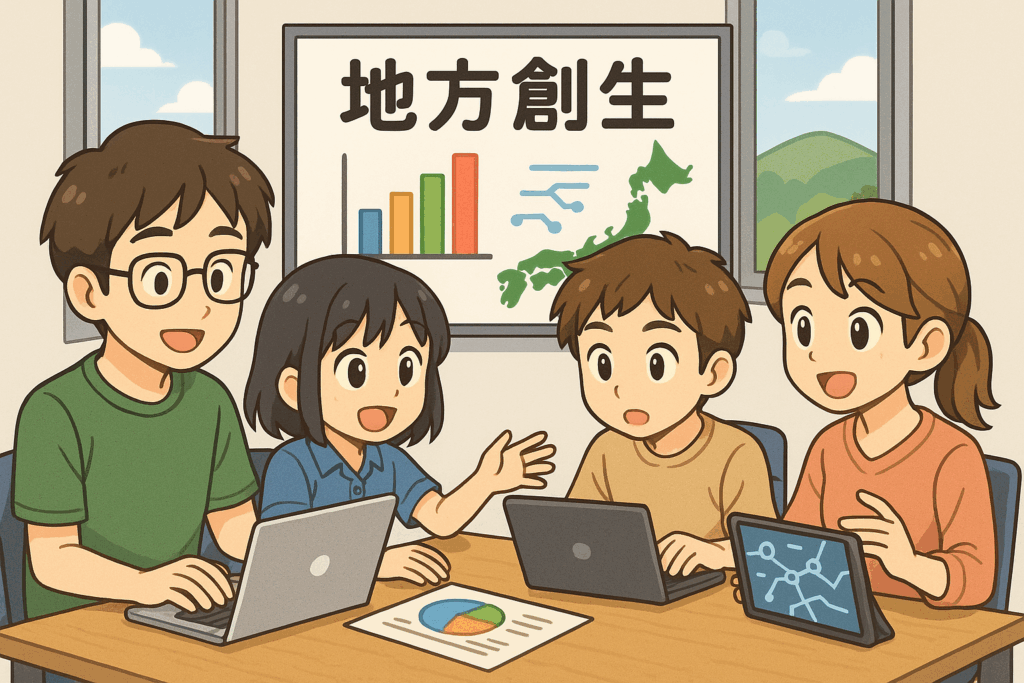
地方創生サークル(ACAS)はどんなサークル?
「地方創生サークル(ACAS)」は、ふるさとの魅力を再発見して発信し、もっと誇れる地域をつくろう!という思いで活動している学生サークルです。
徳島や能登をはじめ、各地の文化や人にスポットを当てて、「こんなに面白いところがあるんだ!」をクリエイティブの力で届けています!
サークルができたきっかけ
代表が「徳島って何もないよね」っていう空気に違和感を持ったのがスタート。実際はアニメスタジオや美術館など魅力がたくさんあるのに、地元の人すら気づいていない…。
そのギャップを「創作」で埋めたい!という想いから「ACAS」が生まれました。
「ACAS」の由来と想い
「ACAS」は Area Create for Artist Summit の頭文字。
要するに「大きなお金や立場がなくても、イラストや音楽、文章、プログラミングみたいな創作活動なら誰でも地域に貢献できる」という意味が込められています。
地方創生サークルの主な活動
奥能登PRサイト制作(進行中)
非公式キャラクター、民謡アレンジ音源、現地取材記事を統合したPRサイト。代表は千枚田や輪島塗の工房を訪ね、素材を収集。イラスト/音楽/記事/実装の分業で制作中。
・ダンスサークルとの地域コラボ
能登でダンスを届ける取り組みを実施。未経験者でも丁寧な指導で成功体験に。
・テーブルゲーム開発
地方創生を題材にしたボードゲームを企画し、楽しみながら学べる形を模索。
活動は隔週ミーティングがメイン。雑談やゲームを挟みつつ、和気あいあいと進んでいきます!
どんなメンバーが集まっている?
イラスト、音楽、文章、企画、プログラミングなど得意分野はバラバラ。
でも共通しているのは「穏やかで、好きなことにめっちゃ熱中するタイプ」。
新しい仲間もあたたかく迎えるので、初めてでも安心です!
メンバー間で大切にしていることは?
今後は佐賀のPRサイト制作や「祈りの投票箱プロジェクト」といった新たな挑戦にも取り組む予定で、地方創生に関心がある人はもちろん、自分の創作を形にしたい人や仲間と何かを作りたい人にとっても魅力的な場となっています。そしてサークルでは以下の2つを大切にしています!
①得意分野を活かす
苦手なことは無理にやらなくてOK。分業で最高のアウトプットを目指します。
②気楽にやる
「地方創生ってよくわからない」でも大丈夫!就活に役立てたい、友達が欲しい、創作を形にしたい…どんな理由でも歓迎です。肩の力を抜いて、一緒に楽しみましょう。
地方創生サークルはこんな人にオススメ!
・自分の創作(絵・音楽・文章・コード)を“公開作品”として形にしたい
・地域の良さを発見して伝える編集力・発信力を鍛えたい
・就活や将来に向けて、チームでの制作実績を作りたい
・地方創生に興味はあるけど、まずは気楽に始めたい
ZEN大学はITに関する授業に特化した学校なのでサイバーなイメージがあり、ITやAIを通じて社会に貢献していくイメージがありますが、そのITやAIを駆使したり、人間一人ひとりの力と情熱で社会に貢献していくことも行っています。
とくにZEN大学から社会に貢献しているのが
ZEN大学地方創生サークルです!
地方創生サークルでは、日々一人ひとりが・その一人ひとりが集まって地方でできることを考えて実行しているサークルです!
佐賀のPRサイトや「祈りの投票箱プロジェクト」など、新しい企画も進行中!
地域の未来にワクワクできる人、創作を通じて仲間と何か作りたい人にはぴったりのサークルです!
地方創生サークル代表者インタビュー
今回サークル紹介を作成するのに大変お世話になった地方創生サークル代表者の「牡丹」さんへZENニュースがインタビューをさせていただきました!

本日はよろしくお願いします!

よろしくお願いします。

さっそくですが、サークルを結成したきっかけは?

私がサークルを結成した理由は、地方の衰退に歯止めをかけたいと考えたからです。

両親の故郷が徳島県なのですが、徳島の方々の中には「徳島には何も無い」といったように、故郷に対して悲観的なイメージを抱いている人が多くいます。実際に、2022年に行われた「住民による都道府県・魅力度ランキング」では徳島が最下位という結果になりました。

どういう集計かわからないですが、徳島には魅力もたくさんあるのでは?

その通りです。客観的に見れば徳島には誇れる資源が数多くあります。例えば、アニメ『鬼滅の刃』を手がけたufotableのスタジオや、米津玄師さんが紅白歌合戦で歌唱を披露した大塚美術館など、全国的に知られる文化的な拠点が存在します。

ところが、地元の方々にはこうした魅力が十分に認知されていないのが現状です。その結果、地域住民自身が「自分の故郷には価値がない」と無意識のうちにネガティブキャンペーンをしてしまっているのです。

この課題は徳島だけの問題でしょうか?

この現象は、徳島に限った話ではありません。これまで様々な都道府県出身の方と話してきましたが、同じように自分の故郷を過小評価しているケースを何度も見てきました。地方全般に共通する課題だと感じています。

私はこの認知のギャップを創作の力を通じて解消し、人々が自分の故郷を誇りに思える社会を形成することで、地方創生を成し遂げたいと思いこのサークルを結成しました。

アーティストサークル(ACAS)の由来は?

元々は「地方創生サークル」だけだと堅苦しいかと思い、「Area Create for Artist Summit」の頭文字をとって名付けました。このACASという名前には、クリエイティブ活動が持つ無限の可能性への期待が込められています。

と言いますのも、地方創生を目的とした場合、多くの手段が想定されます。

例えば、工場を建設して雇用を生み出すことや、地場産業に補助金や支援金を投入することです。しかし、これらの手段は莫大な資産や社会的立場を持つ人でなければ実行が難しいという現実があります。

その点で、創作活動はどう違うのでしょうか?

クリエイティブ活動を通じて地域の魅力を発信する方法は、経済的・社会的条件を超えて誰でも取り組むことができます。つまり、創作こそが誰もが地方創生に参加できる近道だと考えています。

そのような想いがあり「ACAS」という名前には、「地方創生のためのアーティストサミット」という意味を込めています。創作を通じて地域を盛り上げ、多くの人に故郷の魅力を再認識してもらえる活動を広げていきたいと思っています。

現在はどんなメンバーが集まっていますか?

年齢や得意分野は本当に多種多様です。イラストや作曲、プログラミングが得意な方もいれば、企画や執筆を楽しむ方も在籍しています。それぞれ異なる分野を持ちながらも、互いに刺激を受け合えるメンバーが集まっているのが特徴です。

メンバーの雰囲気を一言で表すと?

基本的には穏やかな性格の人が多い印象です。ただ、自分の得意分野に関しては情熱を持って取り組んでいるのも共通点ですね。例えば新しい企画が出たとき、全体としては同意を示しつつも、疑問点や意見があれば遠慮せずにしっかり伝える、といったやり取りが日常的に行われています。

新しい人でも馴染みやすそうな環境ですね!

そう思います。全体的に和気あいあいとした雰囲気があり、新しい部員が入ったときも自然に温かく迎えてくれるのがこのサークルの良さです。安心して参加してもらえる環境だと思います。

そんなメンバー間で大切にしていることは?

大きく分けて2つあります。1つは「得意分野を活かすこと」、もう1つは「気楽にやること」です。

基本的に私は、その人の得意な分野でしか仕事をお願いしません。誰しも苦手なことを無理にやるとモチベーションが下がりますし、楽しさも半減してしまいますよね。ですから、あるメンバーが苦手なことは、それを得意とする別のメンバーに任せる。そういう分業体制でプロジェクトを動かしています。

それでは「気楽にやること」は?

ここで強調しておきたいのは、「必ずしも地方創生に興味を持つ必要はない」という点です。例えば「就活で有利になりそうだから」とか「友達を作りたいから」という理由での参加も全く問題ありません。

でも「社会貢献」という言葉にはなんだか堅いイメージがありますが…

確かにそういう印象はあります。ただ、私は社会貢献はもっと身近で簡単なものだと思っています。

例えば食事や買い物をすると消費税を払いますよね。社会人なら所得税、喫煙者ならたばこ税なども納めていると思います。それらの税金は行政を通じて道路の整備や社会保障に使われます。

つまり「生きているだけで社会に貢献している」と言ってしまってもいいのではないでしょうか。

新しいく入ろうと考えている人も、まずは気楽でOKという事ですか?

社会貢献だからと身構える必要は全くありません。単に「好きなことだからやってみよう」くらいの気持ちで大丈夫です。ふらっと入って、気楽に、そして楽しく活動に取り組んでほしいと思っています。

サークルでは普段はどんな活動をしていますか?

基本的には二週間に一度のペースでミーティングを開いています。議題はそのときによって違いますが、企画のアイデア出しや進捗確認が多いですね。

ただし、そうした議題はできるだけ手短に終わらせるようにしています。あまり長引くと集中力も切れますし、中だるみしてしまいますから。

ミーティングが終わった後は?

そこからは自由時間です。雑談をしたり、作業を配信したり、ゲームをしたりと、各自のんびり過ごしています。堅苦しい雰囲気はなく、笑いの絶えない場になっていますね。

企画で出たアイデアをきっかけに、メンバーと一緒に出かけることもあります。机上だけでなく実際に足を運ぶことで、新しい発見があったり、交流が深まったりするのもこのサークルならではの楽しさだと思います!

「地方創生」という言葉をどのように捉えていますか?

最初の質問と重複しますが、私は「地方創生」を「すべての人々がふるさとに誇りを持てる社会をつくること」だと捉えています。どんな地域であっても必ず独自の魅力があるはずですが、それを住民の方々自身が理解しているとは限りません。

その中にある課題は何だと思いますか?

地域の魅力がうまく発信されず、結果として住民の方々でさえも故郷の長所を見失い、マイナスイメージを持ってしまうという課題があります。ただ、これは住民が悪いのではなく、その魅力が日常に溶け込みすぎていて見えにくくなっているだけなのだと思います。

「自分の長所を5つ答えてください」と言われても、すぐに答えられる人は多くありませんよね。それと同じで、地域の魅力もそこに住んでいる人ほど気づきにくいのです。むしろ外部の第三者のほうが発見・発信しやすい場合が多いと感じています。

サークルではどのようにそれらの課題に取り組んでいるのでしょうか?

私たちはその地域にある魅力を見つけ出し、内外へ発信していくことを大切にしています。そうすることで、少しでも多くの人が自分の故郷に魅力を感じられるようにしたいと考えています。

これまでにどのような活動やプロジェクトを行ってきましたか?

現在進めている主なプロジェクトは、奥能登のPRサイトの制作です。取材、イラスト、音楽、プログラミングといった役割に分かれて分業体制で進めています。

具体的には能登の非公式キャラクターの制作、古くから伝わる民謡のアレンジ、そして能登の魅力を紹介する記事などを組み合わせて、一つのPRサイトとして発信する予定です。私自身も現地に取材へ行き、観光名所の千枚田や輪島塗の職人さんの工房を訪ねました。

他には、例えばダンスサークルとコラボして地域の方々にダンスを届ける活動や、地方創生をテーマにしたテーブルゲームの開発なども行っています。創作を軸に、さまざまな形で地域の魅力を伝えることに挑戦しています。

活動地域はどのように選んでいるのですか?

能登での活動については、地域復興を趣旨とする法人「焼き塩エイミー」さんからお声がけいただいたことがきっかけでした。そこからご縁をいただき、活動をスタートしています。

ご縁があった形ですね!今後はどのように地域を選ばれるのでしょうか?

今後は、メンバーの地元や、地域連携プロジェクトを通じて関わりを持った地域を中心に活動を広げていきたいと考えています。その中でも特に、全国的にすでにPRされている都市部ではなく、まだ十分に知られていない地方を重点的に取り上げたいと思っています。

活動を通じて学んだことや、嬉しかったことはありますか?

一番嬉しかったのは、想定以上に地方創生に関心を持っている学生が多かったことです!

想定以上とは??

私は元々、別の大学の政治学部に在籍していましたが、そこでは大学のネームバリューを目的に入学した学生が多く、専門分野であっても政治に関心を示さない人が大半でした。そうした経験もあって、ZEN大学に入学したときには「サークルに15人集まれば良い方だろう」と考えていたんです。

ところが・・・?

ふたを開けてみると、想像以上に多くの方が興味を示してくれて、現在では50名近くのメンバーが参加してくださっています。その中でも特に精力的に活動しているメンバーは本当に優秀で、最初は「こんなすごい人に指示を出していいのだろうか」と気後れすることさえありました。

そんな中、今どのように運営に向き合っていますか?

今では、メンバーたちの活動に応えられるよう、私自身も誠心誠意サークルを運営することを心がけています。仲間の存在が、私にとって大きな学びであり、日々の原動力になっています。

お互いを磨き会える素敵な環境なんですね!そんなメンバーとの信頼関係を築く上で意識していることは何ですか?

正直に伝えることを一番大切にしています。良いニュースも悪いニュースも包み隠さず共有するようにしています。

悪いニュースをそのままは難しそうですね・・・

そうですね。やはり士気が下がってしまわないように、言い方には気を配っています。ただ、隠してしまうことが一番信頼を損なうので、誠実さを大事にしながら伝えるようにしています。

先程ダンスサークルと連携と伺いましたが、他団体との連携はどうでしたか?

7月にダンスサークルと連携し、能登で地域の方々にダンスを届ける活動を行いましたが、私自身はダンスの経験がなく、最初は「自分にできるのだろうか」と不安でした。

でも、ダンスサークルの部長がとても分かりやすく指導してくださったおかげで、最終的には無事に大成功を収めることができました!

なかなか別の団体との連携は難しいものですが、地方への気持ちが一つになって成功へと導いたのですね・・・!

今後の連携についてはどう考えていますか?

今後は自治体や日本財団との連携も視野に入れています。そのためのステップとして、現在は実績作りに力を入れているところです。

なにか考えているプロジェクトは?

はい。今後は佐賀のPRサイト作りに挑戦するほか、新しく「祈りの投票箱プロジェクト」を立ち上げたいと考えています。

「祈りの投票箱プロジェクト」とはどのようなものですか?

選挙当日に、その地域の特色を反映したデザインの投票箱を設置するというものです。これにより、地域住民が地元の魅力を再確認できると同時に、その投票箱をSNSを通じて全国に発信することで、地域の魅力を広くアピールすることを目的としています。

このプロジェクトの意義とは?

大きく分けて2つあります。1つ目は「地域の魅力を地域住民に効率的にPRできる」という点です。選挙は地域の多くの人々が参加するイベントであり、市議会議員選挙でも投票率はおよそ40%ほど。例えば有権者が1,000人なら400人が集まります。

祭りや選挙のようにこれほど人が集まる機会はそう多くありません。そこにカラフルな投票箱が置かれていれば目を引きますし、SNSで拡散される可能性も高い。その結果、地域住民自身が意図せずとも地域の発展に貢献できるのです。

もう一つの意義とは?

2つ目は「投票率の向上」です。近年、政情不安を背景に投票率は上がっているものの、まだ改善の余地があります。期日前投票日から「祈りの投票箱」を設置することで、SNSでの拡散を狙いながら投票行動を促し、投票率向上にも寄与できると考えています。

実現に向けた課題はありますか?

もちろん自治体との連携は欠かせません。そのため学内に設けられた地域連携プロジェクトなどを通じて自治体と関係を築き、このプロジェクトを実現させたいと考えています。

活動と学業の両立は大変ではありませんか?

基本的に活動は二週間に一度のミーティングが中心なので、両立はそこまで難しくないと思います。もちろん、取材やイベントなどで実際に活動の場へ出向くこともありますが、それらへの参加は自由です。行きたいときに声をかけてもらえれば大丈夫です。

基本的に活動は二週間に一度のミーティングが中心なので、両立はそこまで難しくないと思います。もちろん、取材やイベントなどで実際に活動の場へ出向くこともありますが、それらへの参加は自由です。行きたいときに声をかけてもらえれば大丈夫です!

最後に、これから入る人・興味がある人へメッセージを!

ゆる〜く活動してるので、ぜひぜひ入ってください!

特に、自分の創作や作品をカタチにしたい人におすすめです!
みんなで楽しくがんばっていきましょー!

ありがとうございました!
以上!地方創生サークル代表者「牡丹」さんとのインタビューでした!
地方への熱意と創作での解決の想いを感じるインタビューでした!
目的は大きなものですが、仲間たちと楽しく目標に向かって進める!そんな情熱のあるサークルですね!
地方創生サークルのまとめ
想いと能力どちらも活かして多くの人の役に立つサークル
ですね!
ただの地方創生という取り組みだけでなく、ZEN大学らしく様々な角度から社会に貢献できる、意義のあるサークルです。
一見堅そうなイメージもありますが、実際はみんな和気あいあいと楽しみながら活動を行っているので、誰でも楽しみながら地方に貢献できる素敵なサークルです!
興味を持った方は気軽に参加してみよう!
そんな地方創生サークルの活動を記者として追いかけ、皆に届けたいという人はゆるっとメディアサークルへどうぞ!